目次
- 人間力を高める本は人生を変える
- これが人間力を高める本!おすすめ17冊だ!
- 『幸福について 〜人生論〜』 ショーペンハウアー
- 『自分の中に毒を持て』 岡本太郎
- 『器の大きい人、器の小さい人』中谷彰宏
- 『反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超合理的な考え方』 草薙龍瞬
- 『超 筋トレが最強のソリューションである』Testosterone 久保孝史
- 『一生使えるプロカウンセラーの傾聴の基本』 古宮昇
- 『自分を操り、不安をなくす 究極のマインドフルネス』メンタリストDaiGo
- 『「すぐやる人」と「やれない人」の習慣』 塚本亮
- 『まんが「ブッダ」に学ぶ穏やかな働き方』 手塚治虫 プレジデント社
- 『まんが「ブラック・ジャック」に学ぶ自分を貫く働き方』 手塚治虫 プレジデント社
- 『何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書』中島輝
- 『まんがでわかる 頭にきてもアホとは戦うな』 田村耕太郎
- 『「動じない心」をつくる85の言葉』植西聰
- 『うまくいっている人の考え方 完全版』 ジェリー・ミンチントン 弓場隆 訳
- 『運命を拓く ~天風瞑想録~』 中村天風
- 『「やさしさ」という技術』 ステファン・アインホルン 池上明子 訳
- 『夜と霧』 ビクトール・フランクル
- おわりに
人間力を高める本は人生を変える

人間力を高める本で、人生の困難を乗り越える
人生には、受け入れがたい悲しい出来事や、乗り越えがたい困難がつきものです。
そんな時、「人間力」 があると、物事の解釈を多方面から考えられ、心の安定を保つ力となります。
それによって、自らを再び前向きな人生へと導くことができるのです。
そもそも「人間力」とは?
一見抽象的な言葉ですが、以下のように定義されています。
人間力の定義 > 「社会を構成し運営するとともに、自立した1人の人間として力強く生きていくための、総合的な力。」 > 出典:Wikipedia
つまり、人間力とは、人生をより豊かにし、生き抜くための知恵や精神的な強さのこと。 これは、単に知識を増やすだけでなく、経験を通じて養われるものです。
人間力を高めるためにできること
困難から立ち直るためには、薬や栄養管理、心理学の知識も有効ですが、 社会と関わりながら生きる知恵「人間力」 を高めることも欠かせません。
そのための一つの方法が 読書 です。
読書は、著者の人生経験を疑似体験できる貴重な機会。 本を読むことで、人生の困難を乗り越えるための「生きる技」を磨くことができます。
本記事では、人生をより豊かにし、困難を乗り越えるための 「人間力を高める本」 を紹介します。
ぜひ、あなたに合った一冊を見つけてください。
これが人間力を高める本!おすすめ17冊だ!
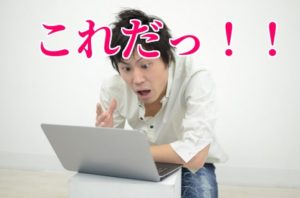
『幸福について 〜人生論〜』 ショーペンハウアー
人間力を高める上で「幸福」について考える事は避けられません。
というのは、人間力を高める本をわざわざ選んで読む理由は、
まさに「幸福になりたいから」ですよね。
19世紀にドイツの哲学者として活躍した、ショーペンハウアーの幸福論は、
幸福を考える上で、その人に備わっている人間力をかなり重視している哲学といえます。
一般的に「人は幸福になるために生きている」と考えられがちですが、
ショーペンハウアーはこの考えに真っ向から対峙するような立場であり
「あまり不幸でない人生」を送ることこそが、幸福になるための本質と考えています。
一見すると、
「なんだかつまらない考え方だな」
とか
「ちょっとネガティブじゃないか?」
と思いますよね?
でも私もそうなんですが、
「自分はもっと人間力を高めたほうがいい」
と思うような状況を経験した人は、この考え方がしっくりくるんですよね。
もともと勉強が得意じゃなかった私は、がむしゃらに勉強して、国家資格を取って、病院に勤めました。
病院に医療職として勤めて、
「もっと認められなきゃ」
とか
「もっと給料あげなきゃ」
と思って、
ある程度の立場と、それなりの年収をもらえるようになったのですが、
やっぱり何か足りないと考えてしまうんです。
結局、その時に「10年後、幸せな自分が想像できるか?」と考えたときに、私は絶望しました。
今のままキャリアを積んで、仮に誰かに尊敬されたりしたとしても、「全然自分は幸せじゃないな」と素直に思ったんです。
仕事もあって、奥さんも子供もいて、持ち家もあって、
勉強が苦手な子供時代の自分からすれば、
まさに、
「すべてを手に入れた状態」
でした。
それでもいろいろあって、うつ病になり、仕事を休んで、働く自信、生きていく自信がなくなってしまいました。
そんな僕を見て、当時母は
「あんたは仕事もあって、子供もいて幸せなんだよ」
と僕に言いましたが、それを言われるとかえって辛かったです。
どんな状況になっても幸せになれない自分が救いようのない人間に思えました。
まさに自分は、
“どんな状況にあっても幸せになれない特殊な人間”
にすら思えてきました。
でもこれ、
全然特殊ではなかったです!!
ショーペンハウアーの考えを知れば、私だけではなく少なくとも、
今の日本人のほとんどの日本人の多くに当てはまるのではないでしょうか。
それでは、人間力を高める本を探している人たちのために、
このアルトゥル・ショーペンハウアーさんの考えを簡単にまとめておきます。
気になったら購入してください。
ショーペンハウアーは、幸福に差を生じさせるための要素として以下の3つを挙げています。
①その人に本来備わっているもの(人間性、健康、道徳心など)
②その人が所有しているもの(資産、家、ブランドバッグなど)
③その人が与える印象(名誉、地位、家柄など)
一般的に、私たちは幸福になる上で、お金がたくさんあり、地位や権力があって、人に尊敬される人生を送ることが大切だと考えがちです。
つまり、②、③が大切だと思われがちです。
確かにそのほうがわかりやすい価値なので、
社長になれば人から尊敬されるし、お金がある人の所には人も集まってきます。
もちろん、異性にもモテるし、そうなったら気分が良いです。
誰よりも、お金や名誉があれば圧倒的に生きやすくなります。
だって意地悪な人からマウントをとられることもありませんしね。
でも、ショーペンハウアーは、
人が幸福になる上で最も大切な要素は、
①のその人に本来備わっているもの、つまり人間性や道徳心、健康面、
つまり、人柄や人間力が最も大切だと言っています。
というか、この①が全てだ!!という勢いで主張しています。
何故かと言えば、お金や車、地位や名誉、ステータスは、他人と比較して初めて価値があるといえます。
例えば年収400万円スタートからスピード出世して3年で課長になり年収600万円になった時、その人はその時はすごく幸せに感じますが、
その人の隣に住んでいる自分より若い男が年収1000万円であると知った瞬間、年収600万円の自分がとても惨めに思えてしまいます。
そして給料を上げるために、3年間努力した価値すらも認めることができなくなるのではないでしょうか。
このように、②、③の要素は誰かと比較して初めて成立する価値であり、また人から奪われてしまう可能性もある不安定な価値といえます。
それに対して、①の要素は「人柄」とか「人間性」とか「健康」などであり、
他人と比較するものではない絶対的な価値観です。
したがって、人生の幸福にとっては、我々のあり方、すなわち、人柄こそ、文句なしに第一の要件であり、最も本質的に重要なものである。
早い話が、人柄と言うものは、どんな状況にあっても、絶えず活動する力を持っていると言う理由からだけでも、その重要性は頷かれるが、なお、その上に、先に掲げた、他の二つの見出しに属する財宝とは違って、人柄は運命に隷属したものではなく、したがって我々の手から奪い取られることがない。
その意味で、他のニ種の財宝が、単に相対的な価値を持つに反して、人柄の持つ価値は、絶対的な価値だということができる。
引用:『幸福について 〜人生論〜』 ショーペンハウアー
つまり「自分はこういう人間でありたい」と思って、
努力していくらでも高めることができるので、他人に認められる必要もなく、自分で価値を決められる絶対的なものです。
高めることによって、自尊心、自己肯定感、自己効力感が得られることもあり、
そして人から奪われることもありませんから、手にしたところで、怯えながら守り続ける苦労もありません。
しかし、生活する上で、最低限の経済的な基盤が必要です。
もちろんそれまでも犠牲にする必要はありません。
ただ、巨額の富を得たり、地位を得たとしても、絶対的な幸福を感じることができない!!とショーペンハウアーはいます。
私たちも際限ない物欲や承認欲はどこから生まれるのでしょうか?
やはり、ショーペンハウアーの考えを知って、自分に当てはめる限り、内面的な豊かさを磨くことが、物欲や承認欲の対処法であると私は思います。
読書をせずに、精神性を磨かなかった時代の私は、とにかくお金を稼いで使うこと、異性にモテることばかり考えていました。
子供が生まれて、高いおもちゃを買ってあげて、その喜ぶ姿が見たい。それができる自分が誇らしく思っていました。
人間の知性や道徳、人間力に何も興味がなかったら、結局そんなお金で解決できるような娯楽に走ってしまいます。
子供にも良い影響が与えられるわけがありません。
そして、そのような行為で得た幸福感は笑えるほどあっという間に消えてしまいます。
給料が上がって、幸せだなって思った時間て、せいぜい3ヶ月位だったかな。
子供に高いおもちゃを買ってあげて、自分が誇らしいと思った時間なんて、どれくらいだったか覚えていませんが、翌日にはなくなっていたような気もします。
そんなことより、人間性を高めてちょっとのことで感情的にならなくなった自分や、他人にたくさん親切できるようになった自分を感じることができる方が、長い時間幸福感を感じられると実感しています。
そうなると、あまり他人の目が気にならなくなるんですよね…。
つまり、承認欲を切り離すためにも自分に備わっている人間性を磨く事が最も近道だとこの本は主張しています。
その他にも、絶対的な幸福を得るために、必要な考え方、働き方などの参考になるので、ぜひ人間力を高める本としてショーペンハウアーの考えをお勧めします。
【”人間力を高める本” 『幸福について』はコチラ】
『自分の中に毒を持て』 岡本太郎
このページにたどり着いた人は.人間力を高めることに興味がある人だと思いますが、
その中には自分の信じる道に自信がなかったり、なんとなく自分の気の弱いところが気になっていたりするのではないでしょうか?
もしくは何かに挑戦しようとしていて、失敗して恥をかいてしまうことを極端に恐れていたり、
そんな自分にイライラする人もいると思います。
この本はそんな人への”劇薬”になります!!
もちろん、人間力も高まるし、
ひょっとしたら「人間力が高まる」なんて言葉では言い表せられないほどのぶっ飛んだ思考が身に付くかもしれません!!
岡本太郎と言えば、多くの人が思い出すのは太陽の塔ではないでしょうか?
私も子供の頃に高速道路から見えた何とも言えない奇抜な建造物に度肝を抜かれました。
一度見たら、忘れられない芸術ですよね。
岡本太郎があの太陽の塔を作るときに、大阪万博の関係者には反対されたそうです。
何といっても、建物の屋根を突き抜けるような作品を作ろうとしていたので周りの人は止めますが、岡本太郎は自分を貫くために、あえて太陽の塔の作成を強行しました。
岡本太郎の作った「太陽の塔」のときの万博のテーマは「人類の進歩と調和」でした。
ただ、これは、表向き、政治的なものです。
あの太陽の塔は、何をモチーフにしているかというと、縄文土器です。
日本最古のアートを万博会場のど真ん中に突き刺したのが岡本太郎の太陽の塔です。(ぶっとんでます、、)
人間が豊かになっていく、便利になっていく。そんな人類の進歩と調和ばかり追い求めていたら、本来の人間の喜び、歓喜などは得られないんだと、岡本太郎は全身全霊を込めて訴えているのです。
私は岡本太郎のこの信念を貫く姿勢が羨ましく、自分にも欲しいと思っています。
この書籍には、人間力を高めるなどの言葉では、表現できないほどのパワーワードがちりばめられています。
・意外な発想を持たないと、あなたの価値は出ない
・迷ったら危険な道にかけるんだ
・好かれる奴ほどダメになる
・きれいになんて生きてはいけない
引用:『自分の中に毒を持て』 岡本太郎
自分には能力がない、自分には強さがない、人間力を高めたいけど、なかなか自信が出ない、そんなふうに思っている人いると思います。
岡本太郎さんに言わせれば、まずはその弱さ自体をありのままに受け入れることが大事になります。
(ここから引用)
自分が未熟だと言って悩んだり、非力を恐れて引っ込んでしまうなんて、よくない。
それは人間というものの考えを間違っている。というのは、人間は誰もが未熟なんだ。自分が未熟すぎて心配だなどというのは甘えだし、それは未熟と言うことをマイナスに考えている証拠だ。
ぼくに言わせれば、弱い人間とか未熟な人間の方が、はるかにふくれ上がる可能性を持っている。
引用:『自分の中に毒を持て』 岡本太郎
自分が弱い人間、自分には人間力がない、自分には能力がない、
そんな自分を認めてしまって、ありのままに生きていけばおのずとやりたいこと、情熱をもやせるものが見つかるとこの本は訴えてます。
そうすると、何かにチャレンジしたり、自分のライフワークになるような生き方が見つかったりします。
そもそもほとんどの人は、相対的な価値観で生きています。
例えば、本当はギターがやりたいんだけど、自分程度の腕前では、人前で弾くなんて恐れ多い。だから、まずたくさん練習してみて、自信をつけてからにしてみよう。
また例えば、本当は心理カウンセラーになって仕事をしたいんだけど、カウンセラーなんて食べていけないから、ましてや独立開業なんて自分みたいな陰キャラ人間には無理。もう少し性格が明るくなって度胸をつけてからにしよう。
また、例えば、絵を描く仕事で、独立開業したいんだけど、今の自分ではとても無理だから、もう少し勉強してからにしよう。勉強して無理そうだったら、やっぱりやめてしまおう。
そんなふうに、自分に条件付けをして行動を制限している人がほとんどです。
岡本太郎は、このような人たちに「無条件で生きろ」と訴えています。
下手でも良い、未熟でもいい、能力が人より低くてもいい、
少しでも魅力を感じたら、少しでもそれに対してモチベーションが出てきたら、少しでもワクワクを感じたら、無条件で行動を起こして、それに全身全霊を尽くす。
失敗したら、また次のことをやれば良い、ただその繰り返しを決してやめない。情熱を感じたら、すぐに行動する、そんなことを繰り返しているうちに、自分の中で燃え上がる何かが見つかります。
結局は、何かを極めた人というのはその分何かを沢山やらかしています。
つまり、失敗を繰り返して、それでも失敗を失敗とも思わず、失敗を糧にして行動につなげています。
そんな中で、人間力が高まっていくので成功者というのは私たちにとって魅力的に感じるのでしょう。
また、本書の中で、読書も強く勧められています。
特に哲学的な本、人生観が得られる本、生き方に関する本などは、それ自体が人生を豊かにし、歓喜の人生に導いていきます。
【”人間力を高める本” 『自分の中に毒を持て』はコチラ】
『器の大きい人、器の小さい人』中谷彰宏
人間力が高い、それはすなわち人間の器が大きいとも言い換えれるでしょう。
著者の中谷さんは某有名大学を卒業し、有名な広告企業に勤務し8年間CMプランナーという厳しい世界で人生経験を培いました。
現在では人生論やビジネス、恋愛エッセイ、小説まで多数の著書を出版し数々のロングセラーを世に送り出しています。
著書を読んでいてわかるのが、中谷さんは会社員時代に様々な理不尽を経験しそれを乗り越えてきたことです。
その中で得た、器の大きい行動や思考パターン、また器の小さい思考や行動パターンを独自の視点でまとめている一冊です。
人間力を高めるために、器の大きい人の思考や行動のパターンを理解して自分の中に落とし込むのはかなり効果的です。
もちろん1度読んだだけでは、すぐに身に付くものではありません。
何度も何度も読んで、それを思い返しまた行動に移す、そのトライ&エラーの繰り返しで徐々に器が大きくなり、人間力の高さになっていきます。
中谷さんはこの著書の中で「器」をこのような捉え方で表現しています。
器の大きい人は、自我も大きくて、それ以上に自己肯定感が大きいのです。
「自己肯定感」から「自我」を引いたものが「器」です。
自我が大きくても、もっと大きい自己肯定感があればいいのです。
自己肯定感の低い人が自我を抑えても、しょせん器の大きさには限りがあります。
引用:『器の大きい人、器の小さい人』中谷彰宏 P 62
これは仏教にも通じるところですが、自我が大きすぎると人生が苦しくなります。
かといって文明社会で生活するうえで、自我を無理矢理抑える事は大きなストレスにつながりかねません。
大きな自己肯定感を自分の中で育むことで、多少大きな自我があっても精神の安定するのです。
そして器の大きな人間としての振る舞いができます。
その他にも器の大きい人間の特徴として、、
・相手にうまく甘えて、助けてもらったり手伝ってもらったりできる
・相手を「できない」のではなく、「教わっていないだけ」と許せる
・変なあだ名を受け入れる
・他人のミスでも謝罪できる
・脇役に回るのができる
・1人の時間を持っている
などなど、
この本で人間力を高めるヒントが盛りたくさん得られます。
【”人間力を高める本”『器の大きい人、器の小さい人』はコチラ】
『反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超合理的な考え方』 草薙龍瞬
この記事にたどり着いたあなたは、
何らかの悩みを抱えており、生きにくさを抱えているのではないでしょうか?
「人間力を高めることでその悩みや生きにくさを解消できれば」
そう考えた事も多いはずです。
私が本を読んで、このサイトにアウトプットする理由もまさにそれです。
実際に、
生きるには苦しみを伴います。
そしてその苦しみからは、逃れられません。
それが世の中の真実です。
しかし、
その苦しみを消す方法はあります。
そして、この生きにくい世の中をお金や名誉の為ではない別のモチベーションで生き抜く術こそ、人生を充実させる方法なのです。
その「別のモチベーション」とは何か?
それがこの本の中にしっかりと記されており、
それこそが、「慈・悲・喜・捨」の精神です。
つまり、人の幸せを願い、悲しみや喜びに共感し、
自我を捨てて許し、譲る心です。
まさにその精神にこそ人間力を高める真髄があるのです。
そしてそのためにまず必要なのは「反応しない練習」。
人間を苦しめるのは、その状況や出来事などではなく、実は自分自身の中の心の反応です。
例え話をします…。
職場の同僚に、
「あなた全然使えないよね」
「〇〇さんがあなたの悪口言ってたよ」
などと明らかな嫌がらせを言われたとします。
そこで余分な判断、反応をしてしまう人は、
「自分は使えない人間、価値のない人間だ」
「自分は人から嫌われている、居るだけでで迷惑をかける人間だ」
「こいつは俺を怒らせたいのか? 人のこと言える立場か?バカ野郎!」
「そんなこと言いやがって、次やったら言い返してやる!」
「そんなことで怒ってしまって、自分は大人げない…。でも同じことされたらまた起こらない自信は無い」
「自分は価値のない人間だ、もう生きていく自信がない」
など、悲しみや怒りとして心の反応を作り出し、無駄に精神を消耗させてしまいます。
そして最終的に極端な判断に走ってしまうかもしれません。

自分の心の反応に気づき、無駄な判断をしない練習をしていると、自然と受け流すことができます。
例えば同じような状況でも、、
「あぁ、○○さんは私にそんな傷つく言葉を言わなきゃいけない状況なんて、○○さんも苦しんでいるんだな」
「○○さんはきっと何か怒りや苦しみを抱えている、でも怒りを抱えている人間に私にやってあげられる事は何もない。無駄な反応はやめよう」
「○○さんにとって私はそのように映っているんだ。ふーんそうなんだ。でもそれは私ではなく○○さんの問題。私は私がやるべきことをただやろう」
そんなふうに 軽く受け流すことが でき ます 。
これが可能になれば無駄な心の消耗がなくなり 、自然と心に余裕が出できます 。
まさに それこそ人間力が高い状態と言えるのでは ない でしょうか ?
人間力を高める事は、ストレスの低下につながります。
そしてストレスが減れば、より多くの社会貢献にエネルギーを費やせます。
この本に書かれている仏教の考え方が、きっと大きな力になるでしょう。
『超 筋トレが最強のソリューションである』Testosterone 久保孝史
人間力を高める本を語る上で、思考(mind)、精神(spirit)の面からお勧めする本はたくさんありますが、そこに身体(body)を加えた本はなかなかないと思います。
もちろん自己啓発本の中に、健康を保つための習慣を強めに取り上げた本はありますが、
体の中でも筋肉に焦点を当てた本はなかなかありません。
でも私は断言します、筋肉は人間力を高めます!
厳密には、
正しいプロセスで筋トレ実行することで人間力は後から高まっていきます。
著者のTestosteroneさんはへ、いまだに正体不明の社長さんで、書籍やTwitterを通じて筋トレを世に広める活動をしています。
この方のTwitterを見たことがある人は多いのではないでしょうか??
本当に面白いです。
たまに私のTwitterの通知にも登場しますが、ちょっと疲れているときにふと目にすると、とんちの効いたギャグに思わず吹いてしまい、それでいてかつ「気づき」が得られるのです。
人間力を高めるにはまさに器を大きくすることが必要です。
心の器を広げる事は、本を読んで気づきを得たり、目の前の人に対して親切にすることで、徐々に大きくなっていきます。
しかしもう一つ、
体の器を広げることも行動力や自信の向上につながり、まさに人間力には重要であることに気づかされます。
筋トレで自信がつく5つの理由
自信がない人は筋トレをしてください。
①身体がカッコよくなる
②異性にモテる
③テストステロンというホルモンが溢れて気分上々
④上司も取引先もいざとなれば力ずくで葬れると思うと得られる謎の全能感
⑤恋人に裏切られてもバーベルがいるという安心感以上の理由から自信がつきます。
引用:『超 筋トレが最強のソリューションである』Testosterone 久保孝史 P204
この本を初めて読んだ時は、
「そんなワケあるかいっ!」
と半信半疑でしたが、
実際に筋トレを本格的にやってみると、
「ホンマや!」
と納得してしまいます。

実際に、脳内ホルモンであるテストステロンが分泌されると、
孤独力や、行動力、そして自信が高まってきます。
そして何より、
「世の中を良くしてやろう」とやる気がみなぎってきます。
そんなポジティブ思考が向上するだけでなく、
メンタル面も安定します。
筋トレすること自体は脳内の幸せホルモンであるセロトニンを誘発するのでそれも科学的に説明できます。
人間力を高める上で、実行力や孤独力、そして精神面の安定は欠かせません。
体の器が大きくなれば、自然と心の器も大きくなり、
「なんとなく頼りになる人」
と自他ともに認める日が来るでしょう。
その時すでに人間力が高くなった自分が存在します。
【”人間力を高める本”『超 筋トレが最強のソリューションである』はコチラ】
『一生使えるプロカウンセラーの傾聴の基本』 古宮昇
カウンセリングを勉強する事は、人の話を聞くことを勉強することです。
なぜ人の話を聞くことが人間力の向上につながるのか?
それは人の話を聞く事は案外難しいことであり、心の中に大きな自我があるとなかなかうまくいかないからです。
そしてこのカウンセリング傾聴術を学ぶ事は、人間理解を深めることにつながります。
人間理解を深めると人間力は向上します。
「この人と話しているとなぜか心が軽くなる」よつな人っていますよね?
そういう人の特徴は、どんなことでも受け止めてくれて、気持ちが温かくなるような存在ですよね?
少なくともすぐ怒るような器の小さい人にそのような人はいません。

著者で臨床心理士の古宮昇さんは、
「聞く技術(傾聴術)を生活の中で生かすことができれば、人間関係を良好にし、大切な人との関係をさらに構築でき、信頼も得ることができるはずです。 」
と本の紹介の中で主張されています。
今の不安定な世の中で、学校や職場などどの環境にいてもたくましく信頼されて、良い関係を築いていくためには適切なコミュニケーション手段が必要です。
コミュニケーション力を高めなくても、傾聴力を高めて共感力を高めることができればこの社会でたくましく生き抜くことができます。
その時既に人間力は高まっているはず。
この本では、信頼関係を築くための聴き方について具体的かつわかりやすく注意点やノウハウが手ほどきされています。
特に人間関係で悩んでいる方や、友達の輪を広げていきたい、他業種の人たちとコミュニケーションをとって自らの世界を広げていきたい方にはお勧めの1冊です。
【”人間力を高める本”『一生使える!プロカウンセラーの傾聴の基本』はコチラ】
『自分を操り、不安をなくす 究極のマインドフルネス』メンタリストDaiGo
人間力を高める上で、マインドフルネスは外せません。
メンタリストDaiGoさんのこの究極のマインドフルネスという書籍は、
人の心の仕組みが盛り沢山書かれており、大いに役立ちます。
結論として、
ほとんどの悩みは私たちが勝手に抱いとるものに過ぎず、
周りの人や環境を変えようとせずに、自分のことを客観的に見て自分を変えていく方が、ずっと生きやすくなります。
このサイトでもちょくちょく言っていますが、
私たちは何のために生きているのでしょう?
私が思うに、私たちは幸せになるために生きています。
それなのに仕事や、学業で必要以上に自信を失い、悩み続けて精神を破綻させてしまうのは本末転倒です。
学生をしていても、社会人になっても生きていればしんどい時は必ず来ます。
そのしんどさに耐えて、最終的に幸せな人生を送る人と、心が折れて病気がちな人生を送ってしまう人、不幸にも自殺を選んでしまう人、その違いは何なのか?
それはどんなときにも、自分を客観的に捉えて行動できるかどうか
の違いだと思います。
例えばこの本には、うつ病になりやすい人の反芻思考について、このように述べられています。
うつ病になりやすい人の反芻思考は、自分の欠点や過去の失敗といったどうしようもないことや、ネガティブなことをずっと考え続けるだけです。
別に解決策を探そうとするわけでもなくただひたすら「自分はダメなんだ、こんな失敗がなければ」と考えるのです。
(中略)
助けてくれる人がいないからうつ病になったのではなく、反芻思考をしていたために、自分の能力が落ち、その結果、周りの人たちが離れていったことが(うつになる)原因であるケースが多いといえます。
出典:『自分を操り、不安をなくす 究極のマインドフルネス』メンタリストDaiGo
私たちは、辛い思いを経験すると、どうしてもそれを蒸し返してクヨクヨと考えてしまう癖があります。
でもそれ自体はおこなっても何の解決にもなりません。
またそのような思考が原因で集中力が低下して、さらに悪い結果を招く可能性が高まります。
それを知っているか知らないかで、随分と今後の生き方が変わってくると思います。
またストレスに関しても、この本では目からウロコのようなファクトが書かれていました。
普段からストレスを避けようとする人ほど、うつになる傾向が強く、人生に対する意義や幸福感を感じづらい
(中略)
ストレスを強く感じていたとしても、そのストレスが自分の力になる、あるいは自分の成長につながると考えていた人は、ストレスの害がなかった
(中略)
ストレスがまったくないと答えている人よりも、ストレスを感じているけど、それは自分にとって成長につながると考えている人の方が、免疫力が高まり、脳が成長して寿命が長くなっていた
出典:『自分を操り、不安をなくす 究極のマインドフルネス』メンタリストDaiGo
私たちはストレスを悪いものだと思って、避けてしまいがちですが、
逆転の発想をしてストレスを良いものと捉えるほうが心と体に良い影響を与えます。
そのストレスのネガティブな要素に対しては、瞑想や読書、運動などで軽減する習慣をがとても大切であると書かれています。
マインドフルネスは、困難が多くて心が動揺しやすい世の中で、いかに心を強くしなやかに保って、社会貢献できる人間になるための重要な手段です。
生きていく上での不安は、無理矢理かき消さなくてもそのままで良い。
不安になってしまうのは仕方ない事。
しかし不安はそのままにして、今自分がやれる事に手をつけていくのが大切です。
その繰り返しが、マインドフルネスな心を育てて、人間力を高めていくのだと考えられます。
【”人間力を高める本”『自分を操り、不安をなくす 究極のマインドフルネス』はコチラ】
『「すぐやる人」と「やれない人」の習慣』 塚本亮
漫画化もされている人気の著書、『「すぐやる人」と「やれない人」の習慣』
は自分の心を律するためにおすすめの1冊です。
人間力を高める事は、自分をコントロールするスキルにもつながります。
怠け心や、優柔不断、気乗りしなくていつまでも行動ができない人は、
徐々に人間力も下がっていき、周りからの信頼も失うでしょう。
そればかりでなく、自分からの信頼もなくなっていき、自分に自信が持てなくなります。
また「すぐやる」習慣がある人は、行動力が高いために、世の中に多くの利益をもたらす事ができます。
だから人間力を高めるために、すぐやる習慣、行動力を身に付ける事は大切です。
私がこの本を読んで、人間力を高める要素があると思った理由は、以下の2つのポイントに絞られます。
1つ目は
「すぐやる人は明日を疑い、やれない人は明日を信じる」(34ページ)
これ「なんで!」って思う人いるかもしれませんが、よく読めば納得できます。
すぐやれない人は、何かを始めようと思う時、
「明日からやろう」とか「いつかこれをやろう」と考えて、未来までモチベーションが維持できると思い込んでいます。
多くの場合モチベーションは維持できずに、やらず終いです。
そんな人に人や仕事が集まってくるでしょうか?
そしてやれなかった自分にレッテルを貼ってしまい、
自己肯定感の低下や学習的無力感を招き、心を病んでいく悲劇にさえつながります。
「すぐやる人」は、未来を信じません。
「明日から」とか「いつか」という考え方は、モチベーションを奪っていくのだと知っているからです。
そしてその「明日」や「いつか」というのは全く保証されていません。
何度も言いますが、実際にその「明日」や「いつか」はやってこないことが多いのです。
もう一つは、
「すぐやる人は抵抗を歓迎し、やれない人は外野の声に潰される」(80ページ)
というくだり、
すぐやれない人は、何かを始めようとした時に、
身近な人の意見や批判的な言葉を聞くと、いともたやすく心が折れてしまいます。
「そんなことあなたには無理だよ」
とか
「そんなに世の中は甘くないから、やめときなって」
だなんて言われると、
とても怖くて未知の領域に挑戦することなんてできなくなります。
一方ですぐやる人は、
“外野は批判的なことを言うものだ”
という人間の習性を知ってます。
そして外野からの批判とは
“大きく飛び立つために必要な風が吹いているようなもの”
と解釈して、外野の批判でさえエネルギーに変えます。
これは、
「本当にやる気があるのかどうか?」
と自分を試してくれたり、
「今まで見落としていた弱点に気づかされてくれる」
という大事な存在だったりします。
人間力の高い人が、批判を理由に何かを諦めるような事はしません。
これはまさに本質をついてるなぁと感心してしまいます。
他にもこれまでの凝り固まった常識や価値観を覆してくれるような教えがたくさん書かれている一冊。
気になったらぜひ読んでみてください。
【”人間力を高める本”『「すぐやる人」と「やれない人」の習慣』はコチラ】
『まんが「ブッダ」に学ぶ穏やかな働き方』 手塚治虫 プレジデント社
仏教関連の本で人間力を高める本はたくさんあります。
というか半分漫画として読めますので、心がしんどい時でも1~2日でスラスラと読めます。
また1日寝る前に1ページだけ読むというやり方でも充分に心が癒されるのではないでしょうか。
手塚治虫の名作『ブッダ』を読んだ事はありますか?
単行本だと、全部で12巻程度あり全巻読みきるには、なかなか根気が要る漫画です。
プレジデント社から発行されているこの本は、その『ブッダ』の名場面を集約して、
働く上での心構えや、辛い時にどのような心で乗り切るか?
その答えが漫画と共に描かれています。
働く上で、同僚や上司、顧客に対してイライラしたり、恐れの感情を持ったりする事はありませんか?
または仕事が順調でも、「嫌われる」「いつか足元すくわれる」などと漠然と不安感を抱えていたり、
また昇進して偉くなったが故に自分の時間が持てなくて心が疲弊していないでしょうか?
働いていると、様々なストレスが身に降り掛かります。
お釈迦様の考え方の本質を理解して、
日々生活の中で実行すれば悩み知らずの人生を送ることができます。
・やり返さない勇気を持つ。
「ミスを認めず謝らない」、「メールや電話の返事をなかなかもらえない」…。
もし、あなたがそのような目に遭い、仕返しをしてしまうと、
相手も反発して仕返しの連鎖が続いてしまいます。相手の受け入れがたい行動をあなたがそっと受け入れた時、相手は初めて反省するのです。
そうすればどちらの怒りも徐々に静まり、穏やかな時間を取り戻すきっかけが生まれます。
恨みを消す唯一の方法、それはやられてもやり返さず、忘れること。
最初に手を下げたほうが、そのあと心理的にも楽になれます。
・「勝ち負け」に支配されない。
仕事において、勝ち負けを全く意識しないで働く事は難しいでしょう。
しかし、不必要なライバル意識や競争は避けるべきです。
勝てば恨みを買い、負ければその苦しみに悩まされることになってしまいます。
相手に勝とうとするより、相手と共に幸せになろうと考えること。
誰かを敵視すれば、自分も敵視されることになります。
一部引用:まんが「ブッダ』に学ぶ穏やかな働き方 手塚治虫 プレジデント社
辛い時、しんどい時ほどあなたの感情は掻き乱されて、それをきっかけに人生が不幸になっていきます。
辛い時ほど淡々と、粛々と行動を積み重ねる。
絶対に許せないような相手、そんな相手だからこそ思い切って許してしまう。
しんどいときの行動、人を許すこと、これは人間にとって最も尊い行為ではないでしょうか?
まさに人間力が高くないとできない技です。
でも、
それができれば仕事上の問題は、99%解決します。
【”人間力を高める本”『まんが『ブッダ』に学ぶ穏やかな働き方』はコチラ】
『まんが「ブラック・ジャック」に学ぶ自分を貫く働き方』 手塚治虫 プレジデント社
手塚治虫の名作、『ブラック・ジャック』は知ってますか?
無資格でありながら、圧倒的な技術力でオペを成功させ、
大金を得ていく裏社会の医師ブラックジャックの信念が描かれた本です。
なぜその漫画が人間力を高める本のか?
まさにブラックジャックこそが高い人間力を持っているからです!!

私たちは嫌な出来事があったり、人生がうまくいかないと、どうしてもネガティブな感情に飲み込まれてしまいます。
ついつい責任を他人に押し付けたり、
誰かに依存したり、
現実から逃げて楽な仕事を選んだり、
そんな苦難の生き方を選んでしまって、さらには人間力を低下させてしまいます。
依存したり多数派に乗っかったり、リスクのない仕事ばかり選ぶのは、
一時的に精神が安定しますが、精神的に独立した生活と言えるでしょうか?
これだけ物質的な豊かさが整った世の中なのに、心が不安なのはなぜなのでしょうか?
それは多くの人が、自分を貫く事に目を背けているからです。
ブラックジャックは圧倒的な能力がありながら、あえて無資格で裏社会の人を相手に医療をする医師。
なんともリスキーな人生を選んでいる彼は、なぜ敢えてそんな生き方をしているのでしょうか?
それは、
その生き方が信念を貫く生き方だからです。
自分と世の中を俯瞰できて、
安易な安定を求める生き方ではなく、
信念を貫く生き方こそが、真の心の自由だと確信しているのでしょう。
私も頭では理解していても、なかなか行動はできません。
しかし、ブラックジャックの生き方には人生で迷ったときに、それを断ち切ってくれるようなヒントが隠されています。
例えば、
・自分を制限するようなつながりは、しがらみでしかないので無理に仲間や人脈は作らない。
・やりたい事、得意な事を仕事にする(実はこれは勇気が要ること)。
・みんなから好かれる人より、賛否両論の人間であり続ける。
どんなに孤独になって批判されても、平常心でやるべきことをやる。
それこそがまさに人間力が高い人の能力。
そのヒントがたくさんこの解説本に描かれています。
【”人間力を高める本”『まんが『ブラック・ジャック』に学ぶ自分を貫く働き方』はコチラ】
『何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書』中島輝
人間力を高める本は自己肯定感も高めてくれます。
自分を肯定する力、「自己肯定感」は最近書店でよ言葉ですが、我々日本人は自己肯定感が諸外国と比べて低いと言われています。
自己肯定感が低い状態とは、人生が消極的になり何をやっても不安、新しいことを始める勇気が持てない状態。
悲しいです。
逆に自己肯定感が高いと、何があっても「大丈夫」と思えるようになる。
まさに自己肯定感を高める事は、まさに人間力の向上につながります。
この本はプロの心理カウンセラーが提供する、心を強くするための実践的なメソッドが記されています。
この本によると
自己肯定感は、何歳からでも高められます。
そして自己肯定感を高めるためにはちょっとしたコツが要ります。
そのためにはまず、自己肯定感を構成する6つの構成要素を知る必要があります。
自尊感情→自分には価値があると思える感覚
自己受容感→ありのままの自分を認める感覚
自己効力感→自分にはできると思える感覚
自己信頼感→自分を信じられる感覚
自己決定感→自分で決定できるという感覚
自己有用感→自分は何かの役に立っているという感覚
参考:『何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書』中島輝
本書では、これらを項目別に評価し、読者の足りていない部分が解明でき、
そればかりでなく、これらを瞬間的に高める方法と、
じわじわと高める2つの対処法が提案されています。
例えば自尊感情を高めるために、鏡の前で肯定的な言葉がけをする事は、瞬時に自尊感情を高める行為です。
(例:鏡の前で「私ってイケてる」と声かけをする)
これを定着させるために、普段の言葉遣いを否定的なものはなるべく使わず、
肯定的なものに置き換えられれば自己肯定感は高まり、そして高い状態で定着していくのです。
(例:職場の仲間に声掛けする時も「お疲れ様」ではなく「ありがとう」を多用するようにする)
何気ない行為の積み重ねが、自己肯定感をじわじわと高めていくのです。
自己肯定感が低いのは、育った環境や生まれ持った能力が低いからだとあきらめていませんか?
自己肯定感が低いままだと人生を楽しむチャンスや将来社会に貢献して人生をより良くするチャンスを逃します!
まさに”自己肯定感を高める”とは、人間力を高めて社会に貢献できる自分を生み出すミッション。
「何があっても大丈夫」という感覚を持てれば、
「すべて思い通りの人生になる」という感覚にもつながります。
そんな良い循環を手に入れましょう。
【”人間力を高める本”『何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書』はコチラ】
『まんがでわかる 頭にきてもアホとは戦うな』 田村耕太郎
人間力を高める本としてはやや乱暴なタイトルですが、安心してください!!
ベストセラーになっている本の「まんがでわかる」版があったので、
最初は立ち読みしてたのですが、人間力を高める本だと確信したので掲載しました。
漫画の方が具体例がわかりやすく描かれており、イメージしやすいかもしれません。
あなたの周りにアホはいませんか?
理不尽な嫌がらせをする”アホ”は相手にしない方が良いと、なんとなくわかっていても言われたらついつい言い返してしまう。
もしくは、感じ悪く無視して、その後もその人を避けてしまう。
そんなタイプの人にオススメです。
攻撃に対して言い返すと、さらに反撃されたり、
たとえ運良く論破したとしても、一時的にはスカっとしますが、やはりそれはそれで気分が悪いものです。
相手と同じ土俵に立ってしまった自分、
そんな小さな自分が情けなく感じた経験ってありますよね。
私がテレビの「ス△ットジャパン」を見ても実はあまりスカっとしないのはそのためです。
一方で、どれだけ皮肉を言われたり、
嫌がらせを受けてもサラりとかわして、世の中うまく渡っていける人もいます。
「あんな人になれたらいいな」
と思えるような人間力の高い人ですね。
この著書は、いわゆるアホに喧嘩を売られた時に、
いかにそのアホからの攻撃をかわして、
さらに、
アホの力を利用して自分を優位にする方法論が書かれています。
タイトルだけ見ると
「ちょっと嫌味な内容では?」
と思うかもしれませんが、とんでもないです。
この本に書いている内容を理解して実行すると、
アホな人間たちは、、相手にする価値が無い!
とハッキリとわかるだけでなく(あくまで私の個人的な感想です)、
自分の心を省みて、さらに心に磨きをかける大切さがわかってきます。
戦うべきなのは
アホそのものではなく
アホと戦うなんてアホなことを考えている
自分だからね!
引用:『まんがでわかる 頭にきてもアホとは戦うな』 田村耕太郎
アホに費やす無駄な時間とエネルギーを、あなたの夢を叶えるエネルギーに変えてみませんか。
【”人間力を高める本”『まんがでわかる頭に来てもアホとは戦うな!』はコチラ】
『「動じない心」をつくる85の言葉』植西聰
著者の植西さんは、「折れない心」や「幸福論」に関する著書、まさに人間力を高める本を多数書かれています。
そんな植西さんが集めた
「動じない心」
をつくるための禅語録
のような一冊です。
いくら強い思いがあって、
固い決意を誓ったとしても、
人間はちょっとした風に吹かれて、
心が動揺してしまうものです。
逆に心が動揺しなければ、
多少要領が悪くても、画期的な仕事をやり遂げる事ができるでしょう。
表紙の裏にも、
「自分の心を上手にコントロールし、
幸福な人生を築くヒントが満載!」
と記されています。
人間力が高い人ほど、自分の心をコントロールして、自分も他人も幸せに導いてくれるものです。
ここで1つ著書から、心を強くする禅の言葉を紹介します。
風が吹いて竹が盛んに揺れている。
その影が階段に映っている。
影がいくら揺れ動いても、
階段の塵は全く動かない。
原文:”竹影階を掃って塵動かず” 大燈国師の語録 『槐安国語』より
引用:『「動じない心」をつくる85の言葉 』植西聰
これは、自分が世間からどのように噂されているか?
それを必要以上に気にするタイプの人に向けた言葉です。
噂を気にする意識が強まると、
自意識過剰という危険な状態につながってしまいます。
そんな人に向けて
「周りの人たちにあれこれ言われても、そんな事は、いちいち気にする必要は無い。
動じない心で、自分がやるべきことを淡々とやるべきだ」
とのメッセージを表した言葉です。
所詮は陰口は陰口です。
面と向かって言えない人間の言葉など、自分の人生に何の影響力もありません。
禅語はとても難しい言葉です。
しかし、それを現代風に理解しやすく翻訳してくれているので、
わかりやすくした人生の教訓が、過去の禅僧の言葉によって裏付けされいるように感じます。
だから、
一つ一つ読むたびにとても勇気づけられます。
【”人間力を高める本”『「動じない心」をつくる85の言葉』はコチラ】
『うまくいっている人の考え方 完全版』 ジェリー・ミンチントン 弓場隆 訳
人間性が成熟し、人生がうまくいっている人の特徴は「自尊心」が高い
と著者は主張します。
自尊心とは、本当の意味で自分のことを大切にしようとする心です。
自尊心のある人は、失敗や間違いを犯しても、それを前向きな力に変えてしまいます。
そして万が一他人に批判されても、冷静にそれを受け流し、必要に応じた対応ができるのです。
つまり人生のあらゆる局面に対して、余裕を持った対応ができるので、
幸せで充実した人生を自然と招きます。
そんな自尊心を高めて人間性を成熟させるヒントが100箇条にまとめてこの本に書かれています。
例えば、他人の批判が怖い人は、次の言葉がおすすめです↓
【批判は余裕を持って受け入れる】
あなたは人から批判されたときにどのような対応するだろうか。
実際、そのときのあなたの対応ぶりほど、
あなたの自尊心の状態を明らかにするものは少ない。
自分のことがあまり好きでない人は、他人から批判されると自分の人格が批判されたと感じ、
人間としての価値まで否定されたように思ってしまうものである。
他人から批判された時は次のことを思い出そう。
(1)その批判から何かが学べることがあるかもしれない。
もし自分が間違ったことをしているなら、
それに気づいておくことが自分にとっていちばんの利益になる。
(2)自分の行為に対する批判は、人格批判ではない。
(3)たとえそれが人格批判であっても、相手に協力して自分を批判する必要は無い。
引用:『うまくいっている人の考え方 完全版』ジェリー・ミンチントン 弓場隆 訳
誰しも批判されると、心が乱れ自分を見失いそうになる時があります。
そんな時は、
「ここで人間性が試されるのだ」
「今こそ成長のチャンスだ」
と考える。
それが人間力や自尊心を高める思考パターンです。
自分に向けられた批判に対し感情に流されずに、冷静に対処できたときこそ、
人間的に成熟した証なのではないでしょうか。
自尊心を高めるヒントが、たくさん詰まった1冊です。
【”人間力を高める本”『うまくいっている人の考え方』はコチラ】
『運命を拓く ~天風瞑想録~』 中村天風
日露戦争を、参謀本部の部員として生き抜き、30歳にして結核で生死の境を彷徨い、
それでもなお、ヒマラヤのヨガの生者に導かれ、90まで生き抜いた中村天風さんの生き方を描かれた瞑想録です。
天風哲学は、元世界的テニスプレイヤーの松岡修造さんや、
経営者の稲盛和夫さんなど数多くの著名人も影響を受けています。
人間はどんな時でも、嘆かず、クヨクヨせず、恨まず、人のせいにしないで、
常に積極的な思考で行動すると運命は開けていきます。
これぞまさに、人間力ではないでしょうか。
この時代以降の、多くの自己啓発系の著者も、中村天風さんの哲学にとても似ているというか、
おそらく影響を少なからず受けている事でしょう。
若かりし日に、
「40歳まで生きることができない」
と言われた中村天風さんの運命は、
積極的思考の哲学を身に付けることにより、92歳まで天寿を全うしたのです。
この積極思考の哲学は、まさに人間力と言い換えてもよいでしょう。
人間力を高めると、運命まで味方するようです。
間違ってはいけないのは、
“それを身に付けることにより健康になる”
が目的ではありません。
たとえ身に病があっても、心まで病ますまい。
たとえ運命に非なるものがあっても、心まで悩ますまい。
しっかりここに、うたっえてあるのだけれども、
古い会員の中にも、病のないときには、
口では盛んにこれをいっておいて、
ちょっとでも病に罹ると、狼狽え、騒いでしまって、
もう心どころか、生命の全体を病ましてしまう者がいる。
わかりきったことを教えているんだけれども、わかり過ぎて、忘れてしまうんだ。
否、一切の苦しみをも、なお楽しみとなす強さを心にもたせよう。
苦しいときでも、楽しいときを思い。
宇宙霊と直接結ぶものは心である以上、
その結び目は断然汚すまいことを、
厳かに自分自身に約束しよう。
引用:『運命を拓く ~天風瞑想録~』 中村天風
生きている以上、困難や、病気、また死からは逃れられません。
“たとえ病気になっても運命を嘆かず、
感謝を持って生きれる”
それがこの天風哲学の究極の目標と言えます。
中村天風さんの哲学=人間力です。
この1冊に「積極的人生」の教えが網羅されています。
『「やさしさ」という技術』 ステファン・アインホルン 池上明子 訳
「優しさ」や「思いやり」は、一見簡単そうな言葉ですが、
実は本物の優しさを持つには、少しコツがあり、知っておかなければいけない技術があります。
ステファン・アインホルン先生は、世界トップレベルの時代として知られるカロリンスカ医科大学の分子腫瘍学の教授、またがん専門医です。
また学生が選ぶ最優秀教授に認定されるほど人気であり倫理についての講義公演の名手としても名高く知られております。
アインホルン先生は、人生で真の成功を収めるには、「優しさ「閉じるが必要だと強く主張しております。
まさに人間力の重大な構成要素として、「優しさ」は外せないものです。
この本は正しい優しさを身に付ける手法や、その心構えがたくさん書いてあります。
その中で特に重要なのが、優しさを振る舞うときに、それが見返りを期待しない行為である点です。
結局はそのほうがメリットが多いのです。
私の父はしばしばアメリカ大統領ハリー・トルーマンの言葉を引用してこういった。
「名声を得るのは誰か?それさえ気にしなければ、
素晴らしい偉業をなし得る」
そして父は、いつもこの原則に従って仕事をしていた。
良い仕事をするには、仲間に気前よくある。
その結果、父は医師としても研究者としても、その後は議員としても作家としても成功を収めたのだ。
引用:『「やさしさ」という技術』ステファン・アインホルン
それを知っておけば、あなたの優しさは正しく機能し、
結果的に思わぬ見返りが待っているかもしれません(言ってることが矛盾してるようですが、事実です)。
近年優しさとは、否定的な意味で使われる場合もありますね、、。
「優しいだけじゃダメだ」
「優しい人つまり、良い奴は無能な人間の代名詞」
だなんて言われていますが、
優しさをないがしろにする人に、優れた人間力は備わりません。
優しさを育んで幸せな成功者になりましょう。
『夜と霧』 ビクトール・フランクル
死にたいと思っている人が、谷底から這い上がり人間力を高めていく。
そのことを語る上でこの「夜と霧」という本は欠かせないと私は思います。

当サイトでも、何度もこのオーストリアの精神科医ビクトール・フランクルの本は紹介してきましたし、ロゴセラピーの考え方のエッセンスをここぞとばかりに登場させてきました。
「自分が豊かになる」、「自分が幸せになる」とばかり考えている”利己的な人”は、
人間力を高めるのは難しいです。
またそのような人は、人生のあらゆる局面で苦しみやすく、
不幸になりやすく、また心も体も健康とは言い難いものです。
ビクトール・フランクルは、強制収容所で、死の淵を彷徨ながら絶望を味わい、
何人もの自殺者・病死者を目の当たりにし、最終的に生き延びる事ができました。
その時の極限の状態、絶望の経験から「生きる意味」についての考え方を体系化しこの本が世の中に送られました。
結論をいうと、
生きる意味は?と問われたところで明確な答えはありません。
それを自分自身が考える行為に、人間力を高める秘訣があるのです。
ここで必要なのは、
生きる意味についての問いを百八十度方向転換することだ。
私たちが生きることからなにを期待するかではなく、
むしろひたすら、生きることが私たちからなにを期待しているかが問題なのだ、
ということを学び、絶望している人間に伝えなければならない。
引用:『夜と霧』ビクトール・フランクル
フランクルが提唱する3つの価値、「創造価値」「体験価値」「態度価値」をしっかり理解して未来に希望を持って生きるのが重要です。
フランクルの本を読んで人間力を高めるなら、この3つの生きる価値の概念は欠かせません。
>>辛いとき、死にたいときに知ってほしい。人生を豊かにする3つの価値
そして自分の幸福を求めるだけの人生を手放して、
「人生からの問いかけ」に答え続ける行為こそが、自立した一人の人間としての成長を促します。
おわりに
 人間力を高める本の多くは、共通してある因子が記されています。
人間力を高める本の多くは、共通してある因子が記されています。
中村天風さんの本でも、斉藤一人さんの本や仏教系の本、そしてアドラーやフランクルの心理学の本でも共通する因子。
それは、「人に”与える”ことができる人間になる」です。
それは時に愛という言葉で表現されたり、仏教では慈しみという言葉で表現されたりします。
結局そうすると回りまわって自分が幸せになれますから、利他的になることは最大限利己的な生き方といえます。
そうはいっても、辛いときに本を読むのは、なかなか出来ません。
だからハードルを下げましょう。
どんなに小さなステップでもいいです。
1日1ページでも、1行でもいいんです。
本を読むと確実に人間力が高まります。
【読書で人間力を高めるおすすめ記事】
>>心理学を学んで生きやすくなりたい人のための3つのオススメ本
>>【大島真寿美】女性におすすめ!こんなふうに生きたいと思える小説3冊!
【あなたにおすすめ記事】





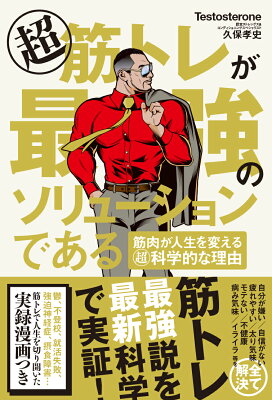
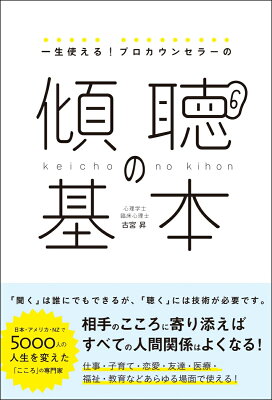



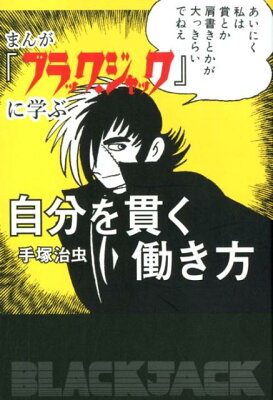









コメント