希望を持つことが、生死を分ける。
「人生をやめたい」
そんな気持ちから抜けられない人、
ぜひ知ってもらいたい話があります。
過酷な辛い状況で生き延びる人と力尽きてしまう人、その違いは何か?
この記事はそこに触れていきます。
目次
希望を持つ人だけが生き抜く??死を選ぶ人は、、。

大きな挫折、絶望を経験した人で、
最終的に自殺してしまう人は少なからずいるでしょう。
しかし一方で不遇を受け入れて、生き方を変えて、違う人生を歩む人もいます。
はたまた、ピンチの経験を生かしてプラスの力に変えて生きる人もいます。
例えばブログで自分の体験記を綴ったり、役立つ情報などを多くの人に伝えて、
そこで希望を持つことにつながり、以前より強い生きる力を得ている人もいます。
そのような人は、そうこうしているうちに精神が落ち着いて、
いつの間にか克服して、以前よりまして幸せになってしまうこともよくあるようです。
希望を持つことでアウシュヴィッツでも生き抜ける??
 希望を持つことの大切さを知るなら『夜と霧』
希望を持つことの大切さを知るなら『夜と霧』
が最もおすすめです。
アウシュヴィッツ強制収容所の生活を描いた名著『夜と霧』を書いた精神科医のビクトール・フランクルは、
自らの収容所経験を基にその答えを出しています。
テレージエンシュタット強制収容所、
アウシュヴィッツ強制収容所、
ダッハウ強制収容所支所、
ティルクハイム病人収容所
の4つの収容所でおおよそ3年の収容所生活をフランクルは生き抜きました。
戦時中の当時ナチスによる迫害を受けたユダヤ人の中で、
フランクルのように生き抜けたのはそう多くないようです。
もっとも過酷と言われるアウシュヴィッツでの収容期間が数日間と短かったのもフランクルが生き抜けた要因の一つと言われてることも確かです。
一方でナチスにより命を奪われる前に、絶望して自ら死を選ぶ人間も後を絶たなかったようです。
収容所の鉄線は高圧の電流が流れており、
自殺の手段を考えずともそれに触れるだけで簡単に死ぬことが出来たのです。
その状況で人々の生死を分けたものは何なのか?
クリスマスのある噂で希望を持つことが出来たが、、

フランクルは、
「未来に希望を持つことが出来たかどうか?」
これが生き抜くカギだったと言っております。
未来に確かな希望を持つことは生きる力です。
逆に希望を持つことが出来ないと、一気に死の誘惑が襲ってきます。
1944年の12月後半から1月初頭にかけてこれまでにない収容所での死者が相次いだようです。
その理由は過酷な労働や飢餓や伝染病でもありません。
「クリスマスには休暇が出て家に帰れる」という噂がそれまでに収容者たちの間で広まり、
その素朴な思い込みが収容者たちの生きる希望になったのです。
しかし実際にはクリスマスに何も起きなかったのです。落胆した収容者は力尽きて倒れていったのです。
人間が未来に対して確かな希望を持つことがいかに生きる力になるかを描いたエピソードです。
フランクルをはじめとした収容所生活を生き抜いた人は、何が起きても未来に対して確かな希望を見失わなったのです。
フランクルにとって書きかけの原稿を著作として世に出すことが、未来への希望でした。
しかし最初の収容所で奪い取られ、それは叶わぬ夢になりかけましたが、フランクルはあきらめませんでした。
フランクルは過酷な収容所生活で、ひそかに原稿を書き直していたのです。
地獄のような強制労働に耐えながら。
「自分の著作は苦難と戦っているすべての人から待たれている。皆が救われる方法を求めている。だから何としてでもこの著作を世に出さなければいけない」
そんなゆるぎない使命感から書かれた原稿、それを世に出すことがフランクルにとって確かな希望でした。
希望を持つことが出来たから、辛い状況でも生き抜くことが出来たと言われています。
おわりに
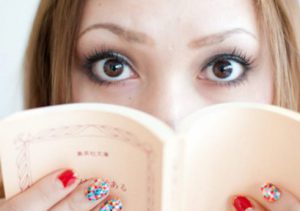
消えない悲しみで苦しんでいる人、人生をやめたいと考えている人、
希望を持ってくださいとは軽々しく言うつもりはありませんが、
自分には希望を持つなんてできないとは思わないでください。
フランクルのように崇高な希望でなくてもいいし、自分が存在しているだけでも誰かにとっては実は大きな救いになっているものです。
私も人生を終わらせたいと考えたことが何度もありましたが、
当時の経験をもとに、人間力を高めていくこと、そしてそれをたくさんの人にシェアすることに喜びを感じています。
以前より人の温かさを感じやすくなりましたし、人の弱さが理解できるようになったので寛容になりました。
そうなると世の中生きやすいのです。
自分自身がいい意味で楽なんです。
ちっぽけな希望でいいんです。
それが絶たれたらまた違う希望を持てばいい。
最初はそのくらいの気持ちで希望を持てばいいんです。
自分には希望つことが出来ない。
まずはそんな気持ちを疑ってみませんか?
<関連記事>



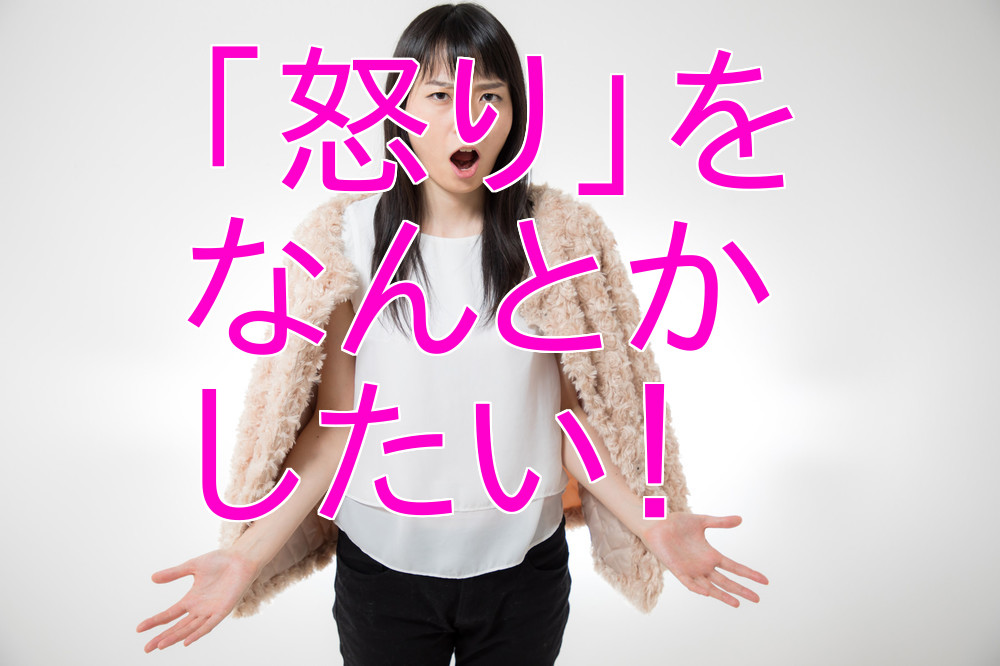
コメント